|
|
|
|
名張市安部田、国道165号線を錦生小学校から
南下すると、道路西側に鹿高神社があります。
その神社境内の山林に、前方後円墳1基、円墳2基の
鹿高神社境内古墳群があります。
左の写真は山林の頂上部にある前方後円墳墳丘。
後円部から前方部。
|
|
|
|
|
|
|
|
前方部から後円部。
この古墳、珍しいことに一墳丘に2基の石室を備えて
います。
下記にマップを作成しましたので参考に。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
後円部石室。
どちらの石室も南西に開口しています。
|
|
|
|
|
|
|
|
・・・開口部狭?!
Σ(・ε・;)
高さ50cmほどしかない開口部。
もちろん・・・
ズサ━━⊂(゚Д゚⊂⌒`つ≡≡≡━━!!
|
|
|
|
|
|
|
|
玄室。
幅2m、高さ2.5mほど、玄室長4.7m。
巨石を用いた巨石墳で、整形された花崗岩?を
用いて組み上げられています。
床面が少し埋まっていますが、そのスケールは
なかなかのモノ。
保存状態もいいようです。
(;´Д`)スバラスィ ...ハァハァ
|
|
|
|
|
|
|
|
埋葬主体は箱形石棺らしく、棺材と思われる板石が
残存しています。
|
|
|
|
|
|
|
|
玄室から開口部。
両袖式。
まぐさ石の巨大さも印象的。
左下にも石棺材が見える・・・
|
|
|
|
|
|
|
|
羨道。
幅1.3m、長さ5.3mあり、石室全長は10mに
達します。
(・∀・)イイ!!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ひときわ狭?!
ガ━━(゚Д゚;)━━━ン!!!!!
・・・もう、明らかに後円部の開口部より小さい!
先ほどは羨道部で腕立て伏せができるくらいの余裕が
あったのですが、こちらはマジでギリギリいっぱい!
文字通り、身体を捻じ込むようにして入室しますた・・・
ズサ━━⊂(゚Д゚⊂⌒`つ≡≡≡━━!!
|
|
|
|
|
|
|
|
けっこう長い羨道をズリズリ進み、やっとこさ玄室へ。
・・・なんだかさっきと雰囲気が違いますな。
幅1.65m、高さ2mほど、玄室長4.55m。
後円部石室よりやや小ぶりですが、使われている
石材が全然違います!
非常に小ぶりな石材を丁寧に積み上げていて、
石室の制作集団が違うことを思わせます。
それに・・・・・あれ?
奥壁に描かれた「中」って何?!
まさか・・・被葬者が毒餃子の国の人
だったとか・・・?
((((;゚Д゚)))ガクガクガクブルブルブル
|
|
|
|
|
|
|
|
こちらの石室には、明確な石棺材が!
やはり、こちらの石室も埋葬主体は箱形石棺だった
ようです。
(*´д`*)ハァハァハァアハァ
|
|
|
|
|
|
|
|
玄室から開口部。
「日本の古代遺跡 三重」には、無袖式とありますが
どう見てもこれは両袖式やろ・・・
( ゚Д゚)ハァ?
画面下にも大きな石棺材が見えますな。
|
|
|
|
|
|
|
|
羨道。
一見しただけで分かるこの狭さ!
長さ3.1mとありますが、体感長さは5mくらいに
感じる・・・
石室全長7.65m。
|
|
|
|
|
|
|
|
さて、こちらは前方後円墳の南山腹にある円墳。
直径15mほど。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
先ほどの円墳のすぐ下にもう1基。
こちらも直径15mほどの円墳。
|
|
|
|
|
|
|
|
墳頂。
こちらも石材などは見当たらず。
前方後円墳の陪塚か?
|
|
|
|
|
|
|
|
鹿高神社境内古墳群 総合評価     |
 ビギナーお薦め度 ビギナーお薦め度 |
  |
開口部がなぁ・・・ |
 マニアお薦め度 マニアお薦め度 |
    |
石室マニア垂涎の一墳丘二石室の古墳。 |
 交通アクセス状況 交通アクセス状況 |
  |
神社境内に駐車場有り。 大型車進入注意。
下車後徒歩約1分。 |
 観賞のポイント 観賞のポイント |
石材の使い方が対照的な二つの石室。 石棺材も必見です。 |
 その他の注意点 その他の注意点 |
 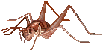 ライト必須。 カマドウマ注意報発令中! ライト必須。 カマドウマ注意報発令中!
夏季はマムシ・ハチに注意。 |
|
|
|